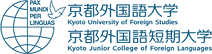日本の伝統文化を
次の時代へ
- 国際貢献学部 グローバル観光学科 1年次生
- 塩見 ミユキ さん
- 滋賀県 日本ラチーノ学院 出身
伝統文化への憧れが、学びの原点に
私は、日本人の父とブラジル人の母の間に生まれました。12歳まで日本とブラジルを行き来しながら、家族内ではポルトガル語で生活していました。京都外国語大学を選んだ理由は、家族と旅行をする中で、日本の伝統文化に触れ始めたことがきっかけです。神社や祭り、着物などの伝統文化に触れる機会が多く、その美しさに心惹かれました。その学びを形にする一歩を後押ししてくれたのが、三井物産が支援する在日ブラジル人大学生向けの奨学金です。両親に学費を負担させたくないという思いから、高校卒業後は約1年3カ月ほど工場で働きながら学費を貯め、資格勉強を重ねて応募に臨みました。選考は課題レポートと面接があり、緊張しながらも自分の思いを精一杯伝えました。合格の知らせは朝のメールで届き、母が涙を流して喜んでくれた瞬間は今でも忘れられません。奨学金のおかげで一人暮らしを始めることができ、先月は両親と一緒に帰国することも叶いました。選考過程でお世話になった三井物産の皆様、そしてご支援くださったNPO法人の方々には心から感謝しています。
私の心を掴んだ『祭り』
入学してから思い切って挑戦したことは、5月に今宮祭を見に行ったことです。学科の必修科目「京都の文化と歴史」を担当する村山弘太郎先生が調査されている祭りで、グローバル観光学科の先輩たちと共に、地元の方が祭壇を作る現場なども近くで観察することができました。組み立てられた剣鉾の行列がパレードのように街を進む際には、私も一緒に横で歩き、そのあまりの綺麗さに深い感銘を受けました。また、西院春日神社の茅ノ輪くぐりにも参加し、本格的な祭礼に触れられたことは非常に印象的でした。「本物の祭り」とはこういうものなのかと実感し、これまで経験した祭りの中でも特に心を掴まれた瞬間でした。日本の祭りの魅力は、なんといってもその歴史にあると感じます。ブラジルの古い行事が数百年の歴史を持つのに対し、日本には千年以上続く伝統行事が多く残っているのです。しかし、衰退が進む現状がある中で、後継者不足や認知不足により伝統が途絶えてしまうのは、非常に残念に思います。こうした経験を通して、日本の伝統文化に対する憧れが増し、今はその継承に貢献したいという気持ちでいっぱいです。
学びの先にある、伝えるという挑戦
京都外国語大学は留学生が多く、留学の機会も充実しています。外国の文化を学ぶ一方で、「日本のことを意外と知らない」と気付く学生も少なくありません。ここでは、日本の伝統や文化を学べる授業もあり、他国を知りながら自国を見つめ直すことができます。その両方を学べる環境が、この大学の大きな魅力だと思います。私自身も、能楽部に参加して「外大能」という大きな発表会に向けて稽古に励んだほか、奈良県明日香村の「Picnic ASUKA」で竹のベンチを作ったり、大津祭で外国人に通訳案内をしたりというボランティア活動などを通して、日本の伝統文化を身近に触れながら経験を積んできました。今後は、京都検定の受験やツアーガイドのアルバイトにも挑戦して、伝統文化の魅力を伝えると同時に未来へと繋いでいきたいです。
※掲載内容は取材当時のものです