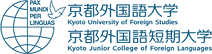恩師の姿を胸に
生徒と共に学び続ける教員へ
- 外国語学部 英米語学科 4年次生
- 久米 真之亮 さん
- 大分県 由布高校出身
私を動かした、恩師との出会い
「自分もこの先生のようになりたい」。高校2年生の時、担任の先生との出会いが英語教員を志すきっかけになりました。もともと私は勉強が大嫌いで、学校での生活態度が良いとは言えませんでした。移動教室の際、授業に行くのが嫌だなと思っていた時も、先生は味方になって根気強く向き合ってくれました。毎日諦めず説得してくれる姿に、自分も次第に「この人のようになりたい」と思うようになりました。そして、英語力を伸ばしつつ、教育を実践的に学べる環境として京都外国語大学を選び、教職課程で多くの経験を積みました。その結果、東京都の教員採用試験に合格。先生に報告した際に喜んでくれた姿を見て、ようやく恩返しができたと実感しました。今後は、授業力や生徒との関わり方をさらに高め、生徒に寄り添いながら、学ぶ意欲を引き出せる教師を目標に努力していきたいと考えています。
現場で実感した「信頼」の力
教育実習では、母校で恩師のクラスの副担任として3週間実習しました。それまでは、「授業が分かりやすければ生徒は安心するだろう」と考えていたのですが、実際には授業外での交流をどれだけ増やしていけるかが授業の質につながると実感しました。初めは生徒との距離感があり、発表する生徒も少なかったのですが、放課後に教室に残って受験相談や雑談の時間を積み重ねることで信頼関係が築かれ、やがて授業中に困ったときには生徒が率先して助けてくれるようになりました。信頼関係の大切さを肌で学んだ貴重な経験です。また、1年間のオーストラリア留学では、異なる文化背景を持つ友人たちと過ごす中で、多様な価値観を理解し、協力し合いながら生活する力が養われ、自分の視野も広がりました。英語力が身についただけではなく、人としての柔軟性や主体性、他者と関わる力を身につける貴重な機会となりました。
英語に向き合うすべての学生へ
大学で外国語の授業を受けるだけでは、語学力がすぐに身につくわけではありません。大切なのは、授業外でもどれだけ自分から言語に触れ、学ぼうとするかです。結局は、自分がどれだけ努力し、継続できるかが語学力向上のカギになります。授業はそのきっかけであり、ものにできるかどうかは自分次第です。私自身も、なるべく英語漬けの生活にしたかったので、家ではできるだけ英語で物事を考えたり、全てのことを英語に置き換えて考えたりしていました。語学である英語は、公式を覚えて解くような数学とは異なり、繰り返し使う中で身に定着していくものだと思います。だからこそ、授業外でも英語に触れる機会を逃さず、自分から“学ぶ環境”をつくっていってください。
※掲載内容は取材当時のものです